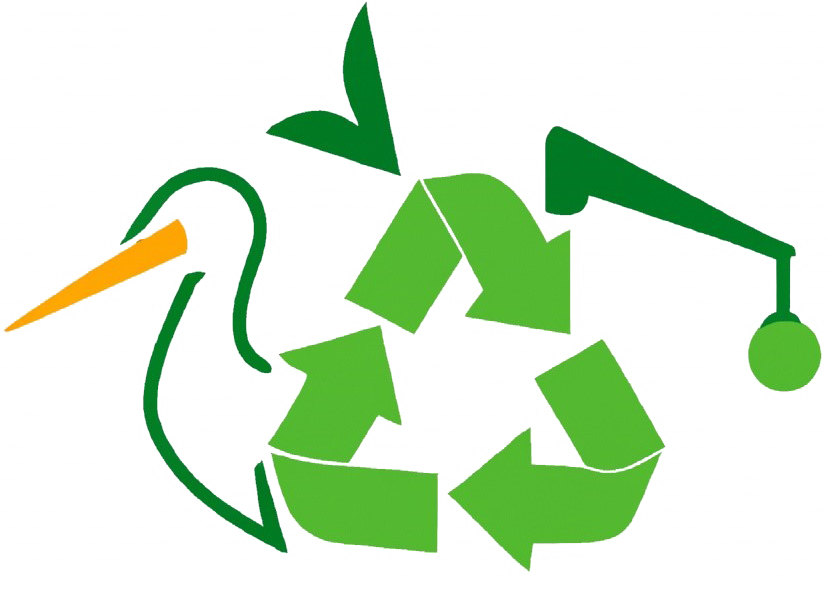30分で終わる!共働き家庭の時短収納術
【共働き家庭の時短収納】
共働き家庭が30分で片付けを終わらせるには、ものの住所を決め、生活動線に沿って収納を配置することが重要です。毎日完璧を目指すのではなく、エリアを区切って集中して取り組む、無理のない仕組みづくりを意識しましょう。
準備:30分片付けを成功させるための3つのステップ
いきなり収納を始める前に、まずは「捨てる」「まとめる」「見せる」の3つのステップを踏むことで、片付けの効率が劇的に上がります。
1. ものの定位置を決める(捨てる)
すべてのものに「住所」を与えることで、探す時間がなくなり、片付けがスムーズになります。
- 1日15分の「見直しタイム」を作る:毎日15分だけ、気になっている場所のものの要不要を見直します。不要なものは思い切って処分しましょう。
- 「とりあえずボックス」を活用する:捨てるか迷うものは、いったん「とりあえずボックス」に入れ、期限を決めて保管します。数か月後も使わないものは処分します。
- 「定数管理」を意識する:食器や文房具など、ものの数を家族の人数分や、用途に合わせて適正量に絞ります。
2. グルーピング収納でまとめる
「使う人」「使う場所」「使うシーン」ごとにまとめて収納することで、出し入れの手間を省きます。
- 帰宅セットをつくる:鍵、財布、パスケースなど、毎日持ち歩くものはまとめて玄関近くの定位置に置きます。
- 身支度セットをカゴにまとめる:朝の身支度に必要なメイク道具、ヘアアクセサリー、アクセサリーなどを一つのカゴにまとめます。
- 食事セットをつくる:朝食で使う食器やカトラリー類は、ダイニングからすぐ取れる場所にまとめ、食事の準備や片付けの時間を短縮します。
3. 「見せる収納」と「隠す収納」を使い分ける
使い勝手のよさとすっきり感を両立するために、ものの種類に合わせて収納方法を選びます。
- よく使うものは「見せる収納」:頻繁に使うものは、手の届きやすい場所にオープン収納します。おしゃれなボックスやかごを活用すれば、見た目もすっきりします。
- 雑多なものは「隠す収納」:郵便物や取扱説明書など、頻繁に使わないものは、引き出しやファイルボックスを活用して隠します。ラベリングをすれば、誰でも場所がわかります。
30分で完了!場所別時短収納術
ものの整理が終わったら、いよいよ場所ごとに片付けの仕組みを作っていきます。
キッチン(10分)
- 使用頻度別に収納する:調理器具はコンロ周りに、よく使う食器は食卓の近くに収納します。
- ファイルボックスを活用する:フライパンや鍋蓋はファイルボックスに立てて収納すると、取り出しやすくなります。
- ストックは定位置を決める:食品や日用品のストックは、ひとつの場所にまとめて置きます。ストックの量がひと目でわかるので、買いすぎを防げます。
リビング(10分)
- 「おもちゃ専用ボックス」をつくる:子どもが遊んだおもちゃは、リビングの一角に設けたボックスにざっくり入れられるようにします。これなら子どもも簡単にお片付けできます。
- テーブルの上のものは毎日リセット:リビングテーブルの上は散らかりがちなので、その日の終わりにはすべて片付けます。何も置かない状態を保つことで、リセットが習慣化します。
クローゼット・衣類(10分)
- たたまず、かける収納:Tシャツやボトムスなど、シワになりにくい服はハンガーにかけて収納します。畳む手間が省けて、時短になります。
- 「ファミリークローゼット」の活用:家族全員の服を1カ所にまとめて収納するスペースをつくれば、洗濯物をしまうのが一度で済み、家事動線がぐっと短縮されます。
習慣化してラクを維持するコツ
- 「帰宅後30秒リセット」:帰宅後、バッグや上着を定位置に戻すことを30秒以内に完了させます。これが習慣になれば、散らかりを未然に防げます。
- 家族みんなで取り組む:片付けは一人で抱え込まず、家族みんなで分担します。ものの定位置やルールを共有することで、協力して片付けができるようになります。
この方法なら、毎日30分という短時間で、共働き家庭でもすっきりとした空間を維持できます。無理のない範囲で、少しずつ始めてみましょう。
前の記事へ
« 高価買取できる家具家電など次の記事へ
捨てられない物を手放すための思考法 »