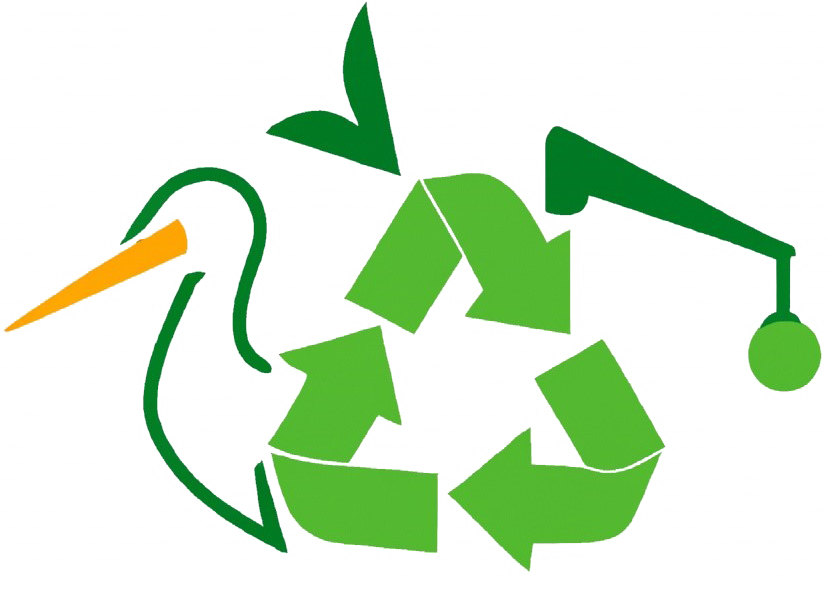悩める高齢化社会
悩める高齢化社会
「老々介護」とは、一般的に65歳以上の高齢者が、同じく65歳以上の高齢者を介護している状態を指します。超高齢社会の日本では、この老々介護が介護世帯の過半数を占める深刻な実態となっています。
老々介護の最新の実態と、それによって生じる主な問題点、そして解決の方向性を解説します。
老々介護の現在の実態
老々介護は今や珍しいケースではなく、日本の介護の主流となっています。
1. 圧倒的な割合の増加
-
65歳以上同士の介護: 厚生労働省の2022年(令和4年)の国民生活基礎調査によると、「要介護者等」と「同居のおもな介護者」の組み合わせで、65歳以上同士の老々介護の割合は63.5%に達しています。これは、同居介護世帯の3分の2近くが高齢者同士で支え合っていることを意味します。
-
75歳以上同士の介護(認認介護を含む): さらに深刻なのが、75歳以上同士の介護も**35.7%**と高い割合を占めていることです。特に、介護者・要介護者の両方が認知症である「認認介護」も老々介護の中から生じる深刻な問題です。
2. 介護者の年齢の高齢化
-
同居している主な介護者の年齢分布を見ると、60歳以上が全体の約8割を占めています。
-
60歳~69歳:29.1%
-
70歳~79歳:28.5%
-
80歳以上:18.4%
-
介護者が高齢であればあるほど、自身の健康リスクが高く、負担はより重くなります。
-
老々介護によって生じる主な問題点
老々介護が深刻なのは、介護を受ける側だけでなく、介護する側の心身の健康と生活基盤が危うくなる点です。
1. 「共倒れ」のリスク
-
体力的な限界: 介護者自身も高齢であるため、要介護者の身体介護(入浴、排せつ、移動など)による肉体的負担が限界を超えやすいです。関節炎や腰痛などの持病が悪化したり、介護者自身が転倒して骨折したりするリスクが高まります。
-
健康状態の悪化: 長期の疲労や睡眠不足、ストレスから免疫力が低下し、風邪や感染症にかかりやすくなるほか、介護うつなどの精神疾患を患うリスクが非常に高まります。
2. 社会的孤立と経済的困窮
-
社会からの孤立: 介護に時間を取られ、友人との交流や趣味などの社会的な活動から遠ざかり、孤立を深めます。これが、介護者の精神的な負担をさらに重くします。
-
経済的な困窮: 介護のために仕事を辞めたり、介護サービス費用が増大したりすることで、貯蓄を切り崩す生活になり、経済的な困窮に陥りやすくなります。
3. 虐待のリスク
-
肉体的・精神的な疲労や孤立が極限に達すると、介護者が冷静な判断力を失い、介護を受ける高齢者への虐待につながる危険性も高まります。
解決の方向性(必要な支援)
老々介護世帯の共倒れを防ぐには、**「頑張りすぎないこと」「専門家を頼ること」**が不可欠です。
-
介護保険サービスの積極的利用:
-
訪問介護(ホームヘルパー): 生活援助や身体介護など、日常的な負担を軽減します。
-
ショートステイ(短期入所): 介護者が休息を取る(レスパイト)ために、要介護者に短期間施設に入所してもらいます。
-
福祉用具のレンタル: 歩行器、車いす、手すりなど、介護者の介助負担を減らすための福祉用具を積極的に利用します。
-
-
地域包括支援センターへの相談:
-
介護生活に不安や負担を感じたら、まずは地域の地域包括支援センターに相談することが重要です。保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員といった専門家が、介護保険の申請からサービス利用支援まで、包括的にサポートしてくれます。
-
-
家族や地域のネットワークの再構築:
-
兄弟姉妹などの親族間で役割分担を見直すことや、地域の見守り活動やボランティア活動を活用し、一人で抱え込まない仕組みを作ることが求められます
-
前の記事へ
« 親世代が納得する物の手放し方次の記事へ
家財(ソファ・冷蔵庫)の吊り作業 »